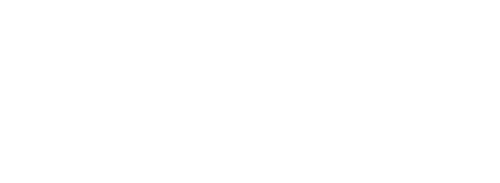市町村別のお茶の生産量日本一の南九州市知覧で、若者と一緒にお茶の新しい楽しみ方を追求していくTEA LABO(ティーラボ)がはじまっています!

「若者に向けて、お茶の消費拡大ができないか?」
お茶の生産地である南九州市には、市民課、納税課といったような行政機関の中に茶業課というお茶を取り扱う部署があります。
その茶業課で、2019年の11月ごろに生まれた1つの相談事が、TEA LABOがはじまるきっかけとなりました。
それは、「若者に向けて、お茶の消費拡大ができないか?」
ペットボトルでお茶を飲む機会は多いけれど、リーフ茶(茶葉)を飲む回数は減っていることや、生産地だからこそ感じるお茶の価格低迷など。
わたし達日本人にとって身近な存在であったはずのお茶が、近年、求められなくなっていることに対する危機感から生まれた問いでした。

「情報がないのに、消費拡大は無理だ!」
若者のお茶の消費拡大について相談を受けたのは、同じく南九州市にある頴娃町で、地域を巻き込みながらさまざまな事業を展開している、株式会社オコソコ 代表の蔵元さん。
さあ、どんなアイデアが浮かぶのか…? と思いきや、
「そもそもお茶について情報を提供できていない現実がある中で、消費拡大を目指すのは無理だ!」と本質を突いた結論が生まれます。

しかも新型コロナウイルス感染症の影響で、人と人が直接会うことをあまりよく思われない昨今。
お茶会や試飲体験など、複数人が1ヶ所に集まるようなイベント企画は難しい状況でした。
そこで閃いたのは、インターネットを使ったお茶の体験プロジェクト。
知覧という場所に若者が集まるのは難しいけれど、オンラインだったら全国の学生と繋がれる! ということで、最初の問いが生まれてから約10ヶ月後の2020年8月に、インターネットを使ってこんな募集を行いました。
限定100名! お茶のある暮らしを一緒に楽しもう!
【8/24(Mon)~限定100名募集開始!】TEA LABOメンバーでお茶のある暮らしを一緒に楽しみましょう
というタイトルがつけられた記事が、全国のお茶に興味を持つ若者=学生に向けて公開されました。

約1ヶ月の募集期間で、応募があった学生の数は、定員を大幅に超える168名。
そこから選考を行い、なんとか定員の100名に絞り、TEA LABOメンバーが決定しました。
北は北海道から南は沖縄まで。中には海外の大学に通っている学生や、高校生の参加もあり、まさに全国の学生とお茶を起点として繋がった瞬間でした。
お茶を楽しむTEA LABO、本格的に始動!
「そもそもお茶について情報を提供できていない現実がある中で、消費拡大を目指すのは無理だ!」という本質的な結論からはじまった、TEA LABO。
100名の学生と繋がったとはいえ、お茶に対する知識や経験は人ぞれぞれ。
そんな状態の中で「お茶の楽しみ方を一緒に考えてほしい」と言われても、学生側は困ってしまいますよね。
ということでプロジェクトのステップ1は、全国のTEA LABOメンバーに知覧茶を届けるところから。


そして、ステップ2は、Web会議サービスを利用して、TEA LABOメンバーがお茶農家さんや南九州市茶業課の方々と繋がる時間を設けました。


テップ2の最後では、ステップ3の案内としてラボメンバーに向けて「自分なりのお茶の飲み方」を考えるが宿題として出されました。

ステップ4では、再びオンラインで繋がる場を設け、自分なりのお茶の飲み方発表会を行いました。
100名100通り。
お茶と相性の良い地元の銘菓の紹介があったり、手作りのケーキと共にお茶を味わったり。
好みの茶器を使ってお茶を淹れたり、氷だしによって濃縮されたお茶の味わいを楽しんだり。
また、ミントやライムと合わせたモヒーティーや、手作りのシロップとかけ合わせたセパレートティーを提案する参加者も。
さらには、お茶を飲むだけでなく香りまで楽しめる、と茶香炉を紹介する学生がいたり、市販の水筒に取り付けられるフィルターを3Dプリンターで自主製作した学生もいました。
発表の形式もさまざまで、写真やスライドを使って表現する学生はもちろん、スマートフォンで撮影した動画で内容を伝える学生も。
「お茶の可能性ってまだまだこんなに広がるんだ!」
「知らなかった楽しみ方がいっぱいある」と驚きの提案がたくさんありました。
事務局サイドの我々だけでなく、参加者にとっても新鮮な情報があったようで、チャットがすごい勢いで更新されていました。


100通りの発表を通してTEA LABOメンバーのお茶に対する親しみや愛情に触れ、先細りするばかりだと思っていた知覧茶の未来って、実は明るく書き変えていけるのでは? と思い直すことができました。
ステップ4の最後には、若者とお茶の関係性の実態を掴むために、事務局からアンケートのお願いがありました。


これらで得た情報は、若者とお茶に関するデータとして南九州市で管理・保存され、生産地から仕掛けるお茶の拡大・消費を考える際の参考にしていきます。
これまで手元になかった若者とお茶のデータを収集できたことは、本プロジェクトの大きな収穫となりました。
データを手にする前は「若者がお茶を飲まなくなっている」
「若者はお茶を好んでいない」といった認識をしている部分が少なからずありましたが、アンケート結果を見ると、お茶を愛している若者は想像以上に多く、間違った認識をしていたことがデータを取得できたことで判明しました。
ステップ5の冊子にまとめる作業は、絶賛進行中!
2019年に生まれた問いをきっかけに、2020年8月から半年以上かけて取り組んできたTEA LABOも、いよいよ最終段階。
ステップ5にあたる、本プロジェクトの内容を冊子としてまとめる作業は、絶賛進行中です。

今後のTEA LABOの動向については、TEA LABOのnoteやSNSを使って発信していきます。
お茶を楽しむすべての人々に向けて。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
今後のTEA LABOの活動も、ぜひご注目ください。