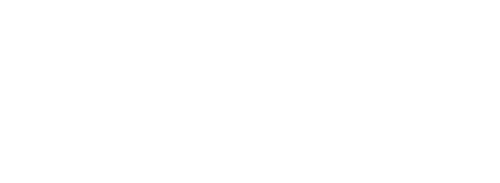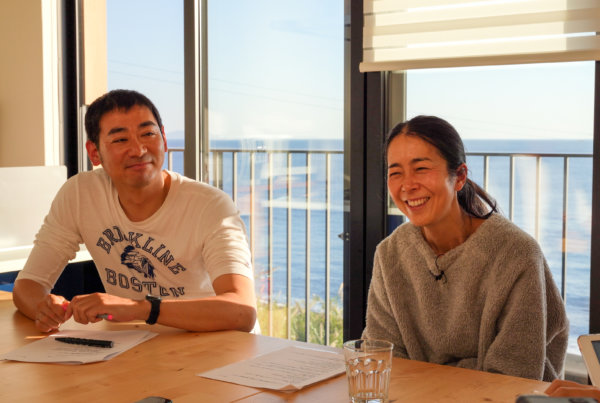2022年1月に開催する
”感情をベースにつながるオンライン交流会”半歩先の歩き方MEET UP
鹿児島県内で”地域内外から人が集まる場”を運営している6組を「半歩先を歩いている方々」と定義し、各地域から1組ずつゲストに招いて地域における半歩先の歩き方についてお話を伺っていきます。
その中で参加者の皆さんと一緒にゲストの想いを深掘りしたり、参加者からの質問にゲストが答えたり(場合によってはそれぞれが抱えている課題を共有したり)といった双方向的な交流会を行います。
※本記事は半歩先の歩き方MEET UP当日の時間につながる、ゲストそれぞれの事前インタビュー記事です。

**
今回は、2022年1月21日(金)19:30〜21:00に登場する長島町 つきひ惣菜店のカイユーヤさんです。
– カイユーヤさんのプロフィール
1993年 大分県別府市生まれ。小学校3年時に見た獅子座流星群に衝撃を受け、理科や宇宙に関心を持つようになる。また両親の影響もあり、料理が身近な幼少期を過ごす。中学校を卒業後は、サッカーのスポーツ推薦で高校に進学。卒業後は、宇宙への学びを深めるために鹿児島県にある大学に進学するも、1〜2年生時の経験を通してアカデミックな分野から変遷し、3年生以降はイベントを行なったり、自主的に招待制の食堂を立ち上げる。その後は、長島町に移住し地域おこし協力隊として活動。現在は「食堂 あさひや」「つきひ惣菜店」の2店舗を経営すると共に、料理人として毎日食べても飽きない料理を提供している。

– つきひ惣菜店とは?
2021年5月にオープンした長島町役場の近くに位置する惣菜店。
”長島町の台所になる”をコンセプトに掲げ、元地域おこし協力隊のカイユーヤさんが店主を務めている。
チキン南蛮や唐揚げといったメインのおかずをはじめ、にんじんのラペやピリ辛ナムルなど副菜も提供。その他、スパイスカレーやお弁当の販売なども行っている。

– 年上の人と過ごすことが多かった幼少期
大分県別府市で生まれた、ユーヤさん。お姉さんが1人います。
幼少期の思い出を尋ねると「小学校から始めたサッカーと、団地で年上のお兄ちゃん達に遊んでもらったこと」と話します。
ユーヤさん:サッカーを始めたきっかけは、同じ団地に住んでいた友達が始めたからですね。名前が同じ”ゆうや”で、歳も一緒ですごく仲が良くて。
母が仕事で帰ってくるのが遅かったりしてたので、その子の家によく家に遊びに行っていて「こいつがサッカーを始めたら遊び相手がいなくなる」と思って僕も始めました。
当時は団地に住んでいたというユーヤさん。
通っていた学校の規模はそれなりに大きかったものの、近所に住む同級生は少なかったようです。

ユーヤさん:小さい時は年上の人と過ごすことが、本当に多かったです。
住んでいた集落もじいちゃん、ばあちゃん達ばかりで町内会のバス旅行に行ったら、僕と姉ちゃんしか子どもがいないことも。
おかげで、すごく可愛がってもらいました。
遊ぶ時も年上のお兄ちゃんとか、先輩達ばかりでしたね。家にもよく遊びに行ってました。

– 獅子座流星群に衝撃を受け、宇宙に興味を持つように
小学校の授業では、理科が好きだったそうです。
ユーヤさん:小3の時の獅子座流星群が、15年に1度くらいの”極大”って呼ばれる、1分間に流れる星の数がすごく多いタイミングで。
その時に見たたくさんの流れ星に、すごく衝撃を受けました。
その時の匂いとか冷たさとかは今でも覚えています。
初めて見る大量の流れ星に、大興奮のユーヤさん。
翌日、その事を学校で先生に話すと、筒に入れたスチールウールが圧縮されて発火する”断熱圧縮”と呼ばれる現象を見せてくれました。
そして先生は、「今目の前で起こった現象と同じことが、昨夜の獅子座流星群で起きていたんだよ」と続けます。
ユーヤさん:先生から、”宇宙にあるゴミが大気圏に突入する時、断熱圧縮が起こって高温になる。その光を見て僕たちは願い事を込めたり、きれいだと思っているんだよ”って話しを聞いて、
規模は違えど、昨日見た流れ星と同じ現象が目の前で再現されていることにめちゃくちゃ感動しました。
そこから「理科って面白いな」って思うようになって、宇宙にも興味を持つようになりました。

その後、中学校に上がっても理科好きは変わらなかったそうです。
またサッカーでは、小学校の少年団からクラブチームへ。
高校生にも勝つようなチームだったそうで、練習は厳しく監督も怖い。中でも走る量は相当だったようで、「何度も辞めようと思った」と話します。
とはいえ、チームメイトに恵まれて、最後まで続けることができました。
そうして高校はスポーツ推薦での進学が決まり、地元の別府市から大分市にある高校に通うように。
– 心地良さを感じていた、チームメイトとの関係性
高校のサッカー部での思い出について伺いました。
ユーヤさん:練習はきつかったけど、中学時代に比べると全然普通というか、乗り切れましたね。
先輩後輩の仲も良くて、”○○先輩”じゃなくて”○○君”って呼んでいたり、上下関係もピッチに入ったらそんなに関係なくて、良い雰囲気のチームだったと思います。

話しを聞いていると、”サッカーにのめり込んだ青春時代”という印象を持ちますが、サッカーを続けた本当の理由は別のところにあるそうで……
ユーヤさん:サッカーがめっちゃ好きだったというよりは、チームメイトに会いに行ってましたね。
高校もそうだけど、小・中学校時代もチームメイトにすごく恵まれて。
いい奴らばっかだったから、練習キツくて辞めたいけど、辞めたらこの子達と会えなくなるよな……と。
本当は辞めても会えるんだけど、その時は何かを共有しているから強い絆で結ばれているというか。
その関係性が心地良くて、すっごい嫌な練習も頑張れていたような気がします。
「誰かと何かをしたり、同じ目標に向かっていく楽しさも知りました」とふりかえる高校時代を過ごした後は地元を離れ、鹿児島県にある大学に進学します。

– 同級生と過ごす中で、自分の本心に近づいていく
大学では、理学部 物理科学科に所属。
進学した背景には、小学校の時に感動した宇宙への学びを深めたいという思いがありました。
ユーヤさん:一般的に1〜2年生では教養を学んで、3年生頃から研究室に入ると思うんですけど、
僕がいた学科の子たちは物理が好きな学生が多くて、その子達と週1回自主的に集まって問題を解いたりしてました。
「何か手伝わせてください」と、研究室のドアを叩いたこともありましたね。
そんな風に物理に対する熱量が高い友人たちと接する中で、ユーヤさんの中にある変化が生まれていきます。
ユーヤさん:同じ学科の子達と過ごす中で、「このレベルが研究者になっていくし、多分もっと上もいる」と思うようになりました。
同時に「自分は探求ができないかも。もしかしたら、物理に対してそんなに興味がないのかも」とも思っていました。
でも理科が好きな気持ちは変わらなかったので、別の方法で関われないかな? と。
周囲とのコミュニケーションを通して、
”ひとつの内容を深く突き詰めていくよりも、人に伝えたり、広げる方が好きかもしれない”と自分に対する認識が変わっていったユーヤさん。

ユーヤさん:専門的な内容を噛み砕いて小学生に教えたりするのは得意だったので「理科の先生になろうかな」と。
元々、高校生の時から教員を目指す気持ちはあったんですよね。
にもかかわらず教育学部ではなく理学部を選んだのは、専門的な探求を行った上で生徒と接する方が、理科好きな人を増やせると考えていたから。
「あわよくば研究者に……」という思いもあったものの、1〜2年生での経験から次第に別の道を考えるように。
その後はアカデミックな分野から変遷して、イベントの企画・実施や学生団体を作ることに注力するようになっていきました。

– 料理は好きというよりは、”苦じゃない”って感じ
現在は長島町で「食堂 あさひや」や「つきひ惣菜店」を経営し、料理に関する仕事をしているユーヤさん。
ここからは少し遡って、料理に触れたきっかけについてお聞きしていきます。
ユーヤさん:父親が飲食店をやっていて、母親も料理上手でわりと何でも作れるようなタイプでした。
小さい時に料理を作る機会があって、その時に母親が色々教えてくれて。
それから1人でも作るようになって、それを母親に食べてもらって「美味しかった」とか「あれが足りないかもね」とか「この作業を飛ばしたでしょう」とか。
そのやりとりが結構楽しくて、最初は料理そのものが楽しいというよりは、料理をきっかけに生まれるコミュニケーションの方が好きでしたね。

また味については、お父さんとの遊びの中で覚えていったと話します。
ユーヤさん:父親のお店は日本食がメインだったので、基本的な味付けが全部できる人だったんですよね。
それで「醤油とみりんを1:1にするとこんな味になります」とかを実際に味見しながら覚えていくというか、そういう遊びをしてくれて。
その中で「これとこれとこれを混ぜたら肉じゃがみたいになって、醤油が多くなると角煮っぽくなるんだな」とか「もう少し薄くしたらこうなるな」みたいな感覚が身についていきました。
そうした両親とのコミュニケーションを通して、小・中学生の時には既に、ある程度の料理が作れるようになっていたそうです。
料理が好きだったわけでは無いんですか? と質問すると、
「好きというよりは、”苦じゃない”って感じですね」と淡々とした答えが返ってきました。
当時のユーヤさん自身にとっての料理は、何のハードルも感じない、当たり前に出来る事。
ところが大学に入り、一人暮らしが始まったことで「料理が作れるって便利なのかも?」と思うようになったそうです。
ユーヤさん:友達と家でご飯を食べたり、サークルでキャンプに行ったりする時も当たり前に僕が作っていたし、それも全然苦じゃなかったんですよね。
3年生以降はイベントに出店して料理を販売したり、招待制の食堂をやったりするようになりました。

– 後に移住することになる長島町との出会い
4年生に進級後は、鹿児島の偉人の1人である”五代友厚”の映画化に関わるプロジェクトに参加するために、前期が終わったタイミングで休学することに。
そのプロジェクトの中で、後に移住する”長島町”とのつながりが生まれます。
そのきっかけは当時、地域おこし協力隊として活動していたある人からの「将来は何するの?」という問いだったそうです。
ユーヤさん:ちょっと話題が戻るんですけど、大学3年生の時に「ゆーや食堂」っていう招待制の食堂をやっていて……
▼ゆーや食堂の仕組み---
①まずユーヤさんが呼びたい学生さんを1人選び、招待状を送る
②その学生さんが会いたいと思う大人を自力なり、他力なりで探してきてもらう
③学生さん、大人の方の2人から食べたいものをリクエストしてもらう
④リクエストを元にユーヤさんが料理を作る
⑤ユーヤさん、学生さん、大人の方の3人で同じ料理を食べながら会話を楽しむ
------
ユーヤさん:”僕らの時代”みたいな場を作りたかったんですよね。
僕らの時代では食事はないけれど、そこに料理があると初対面でも話しやすくなる。
そういう「コミュニケーションのハードルが下がるような場所を作りたい」っていう思いでやってた活動が、すごく自分の中でしっくりきていて「いずれはこういうことを仕事にしたいな」と。
とはいっても、それは今すぐに! というよりは、まずはどこかに就職をして、10年ぐらい経ってから……という風に考えていたそうです。

その正直な気持ちを「将来は何するの?」と問いかけた協力隊の人に伝えると、
「それ長島町でやってみない?」
ユーヤさん:「協力隊って3年間の任期だけど合わなかったら1〜2年で辞めることもできるし、今23歳でしょう? 25〜6歳で辞めたとしても第二新卒とか大学院に行った子達と同じぐらいの年齢だから良いんじゃない?」みたいなことを言われて、そっか確かにと思って。
色々考えたけど、やりたい気持ちの方が大きくて、長島町の協力隊になることを決めました。
その後長島町に移住し、4ヶ月ほどが経ったところで復学。
4年生の後期は、長島町から大学に通い、卒業したそうです。

– 地域に入る時に料理があって本当に良かった
地域おこし協力隊として長島町での活動が始まったユーヤさん。
最初の半年間の活動について伺いました。
ユーヤさん:他の隊員の人は「プログラムができます」とか「ずっと営業してました」とか「前職で企画やってました」とか色々スキルを持っていたけど自分にはそういうのが全くなかった。
だから最初の半年ぐらいは町民の人のところに行って、話しを聞くことが多かったですね。
特に子育てサロンと呼ばれる、お母さん達が集まる場所によく足を運んでいたそうです。
ユーヤさん:お母さん達と色んな話しをする中で「晩御飯を作るのが大変」って話を聞いてたから「じゃあ僕が作ります!」と。
その代わり、3家族ぐらい連れてきてもらえませんか?って伝えて、複数の家族のご飯会に僕が料理担当として入るっていうのをやってました。
金額については、食材費のみをいただく形を取っていたそうです。
そうやって長島町で暮らす人達の台所を使わせてもらう機会が増える度に、知っている顔も少しずつ増えていきました。
ユーヤさん:地域に入る時に料理があって、本当に良かったです。

料理を入り口に地域との関係性を作っていったユーヤさんですが、美味しい料理が作れるとはいえ、移住して数ヶ月の青年が他所の家の台所を使うことは簡単ではないはず。
その辺のコミュニケーション方法について、何か秘訣があったのか尋ねてみると、
ユーヤさん:幼少期の話題で団地の話しをしましたけど、団地も小さなコミュニティなんですよね。
僕自身、小さい頃に歳上のお兄ちゃん達と過ごす中で「こういう立ち振る舞いをした方が良いな」とか「こういう言葉を使った方が物事が円滑に進むな」とかが染み付いていて。
おばあちゃん達と話す機会も小さい頃から多かったので、そういうコミュニケーションは割と得意だったというか、違和感なくできるというか。
地域に入った時に、周りの人と摩擦があまり起きなかったのは、小さい頃の経験があったからかな? と思います。

– 協力隊としての最後の1年は「食堂 あさひや」に尽力
協力隊としての最後の1年は、後に食堂となる「あさひや」の立ち上げや営業がメインの活動となりました。
ユーヤさん:あさひやは協力隊みんなで作った会社で物件を購入して、リノベーションをしながら作っていきました。
飲食店の機能は、始めは細々とやっていた感じだったけれど、町からの反応が割と好評だったので、
「じゃあ、ちゃんとした飲食店にしましょう」ってなって、2019年の7月にオープンしました。
そうして地域おこし協力隊として3年の任期を終えた後も、長島町での暮らしを続けています。

– ”長島町の台所になる”がコンセプトの「つきひ惣菜店」
「食堂 あさひや」のオープンから1年10ヶ月が経った、2021年5月には「つきひ惣菜店」の営業をスタート。
ユーヤさんが関わる飲食店としては、2店舗目となります。
「つきひ惣菜店」のコンセプトは、”長島の台所になる”
食料自給率100%を超える長島町の食材を使ったお惣菜をはじめ、カレーやお弁当なども販売しています。

ユーヤさん:つきひに来てくれるお客さんは、99%長島町の人ですね。お母さん達から、おばあちゃんとかおじいちゃんも。
協力隊の時に関わりがあった人も多くて、3年間の活動はすごく大きかったな、と思っています。
**
オンライン交流会当日は、「つきひ惣菜店」や”長島町での暮らしの中で感じること”といったお話しをメインに伺っていきます。
長島町のカイユーヤさんが登場する「半歩先の歩き方MEET UP」は、2022年1月21日(金)19:30〜21:00です。
参加申し込みと事前質問は、こちらから(参加無料)↓
詳細については、Facebookイベントページまたは、EIGOの参加者募集記事をご覧くださいませ。
− オンライン交流会当日は、FacebookまたはYouTubeから
開始の時間になりましたら、EIGOのFacebookページまたは、YouTubeアカウントからご参加ください。
**
半歩先の歩き方MEET UPは、鹿児島県から「つなぐ・つながる連携の場づくり事業」を受託したNPO法人頴娃おこそ会が実施いたします。
– 本事業の概要をまとめた冊子が完成しました!
(2022年4月追記)
「”感情をベースにつながるオンライン交流会”半歩先の歩き方MEET UP」の概要をまとめた冊子が完成しました。
冊子の中には本事業の中で生まれた大切な言葉の一つである、
”地域をつくっているのは「感情を持つわたし達ひとりひとり」である”
を1ページ目に明記し、県内6地域で活動されている方々のインタビュー記事(EIGOで公開したものと同じ内容になります)を掲載。
また、2週にわたって6日間の開催となった「半歩先の歩き方MEET UP」の舞台裏や、交流会の様子についてまとめています。
全40ページにわたる冊子の内容は、下記からPDFデータでご覧になれます。
県内の何処かで冊子本体を見つけた際は、ぜひ手に取ってみてくださいね〜!