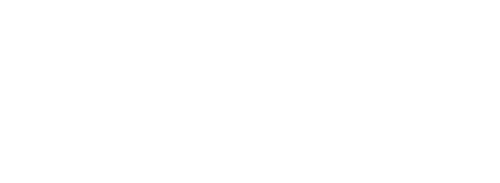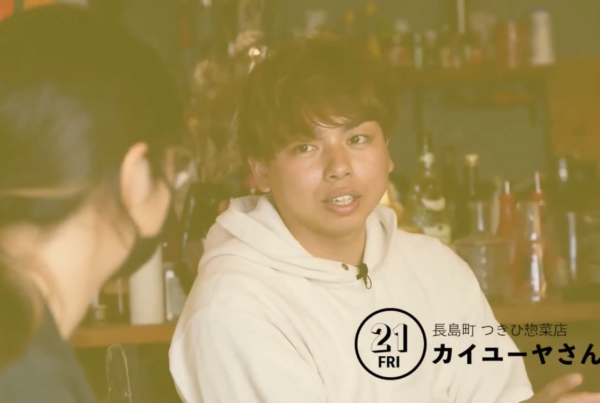”感情をベースにつながるオンライン交流会”半歩先の歩き方MEET UPが、2022年1月14〜16日、21〜23日の6日間開催されました。

▼半歩先の歩き方MEET UPとは?
▼ゲストのインタビュー記事を先行公開
交流会に先立ってゲストそれぞれの幼少期〜社会人生活の中で印象に残っていることや現在の活動に至るまでの背景をまとめた「半歩先の歩き方MEET UPにつながるインタビュー記事」を先行公開しました。
本記事は、半歩先の歩き方MEET UP 当日のアーカイブ記事です。
当日の様子をそのまま記録した動画は、EIGOのYouTubeチャンネルからご覧いただけます。
– 1/23のゲストは、錦江町 ゲストハウスよろっで 山中陽さん

・山中陽さんのプロフィール
1992年 福岡県遠賀町出身。高校卒業後、小学校教員の免許取得のために大阪にある教育大学に進学。卒業後は小学校の先生として2年間を過ごす。その後は民間企業へ転職し2年ほど働いた後、2019年4月に錦江町へ移住。地域おこし協力隊として”空き家活用”をミッションに地元の人達と共に「ゲストハウスよろっで」を開業。現在は錦江町で起業した”株式会社燈(あかり)”と”株式会社hinata”の2社で代表を務めている。
※一部ライティングは、錦江町の地域おこし協力隊 友安麻里亜さんにお願いしました。
− ゲストハウスよろっでのカウンターから
山中さんはバータイム営業中の「ゲストハウスよろっで」(以下、よろっで)から参加。
マイクから利用者の笑い声が聞こえてくる賑やかな雰囲気の中、錦江町の地域づくりについてお話しを伺いました。

− 錦江町について
錦江町は、鹿児島県 大隅半島の中南部にある人口約7000人の町。
海と山に囲まれていて、お茶やサツマイモ栽培など一次産業が盛んです。
高齢化率は45%を超えていて特定過疎地域に指定されていますが、そんな厳しい現実を逆手に取って、子どもや孫に錦江町の未来をつなごうと町づくりにチャレンジしています。
− ゲストハウスよろっでについて
・「屋根の色は何色にしようか? 」
よろっでは元々「浜園商店」という飼料やお米を販売するお店でした。
長年空き家状態でボロボロだった店舗を役場が買い取り、町民と協力しながら少しずつ改修していきました。
町のみんなでつくった小さな居場所が「ゲストハウスよろっで」です。
・よろっでの目的は飲食店ではなく、人のつながりを生むこと
町づくりにおいて山中さんが大切にしていることは、「宿泊するゲストとの交流を大切に。地域の人との交流が生まれる場所に」
よろっでを訪れた人が心地良く過ごせたり、ひとりひとりと丁寧なコミュニケーションが取れることを軸としています。
また一日店長など地域イベントの開催や、自然発生的に生まれる町民とゲストの団らんを大切にしています。

− よろっでに関する質問など
・よろっでのお客さんは町外・町内どちらが多いですか?
全体的には町内からの利用が多いです。
宿に関しては町外からの利用者が多いけれど、飲み会の時にタクシーの代行を呼ぶ代わりに宿泊してくれる町の人もいます。
ランチ・バータイムの時は、地元の方もよく利用してくれます。インスタ経由で来てくれる人もいますね。
バータイムには、町外からの宿泊者と町民さんの交流が生まれることも多いです。
・半行政半民間の形態で苦労したことはありますか?
個人的にはメリットが多いと感じています。
役場の立場にあることを話すと、初めて会う町の人でも安心して接してくれますね。
協力隊の活動経費を空き家の改修費として活用できるし、役場の人も親身になって地元の人をつなげてくれる点もありがたいです。

・都市部からの若い移住者が町づくり活動の中心にいるが、町の人とのコミュニケーションはどのように行っていますか?
よろっでの業務を通して自然と仲良くなっていることが多いです。
町の人と一緒にごはんを食べる機会も多くて、仲良くなった町民さんと出かけることもよくありますね。
よろっでのHPでは、交流の楽しさを発信することで滞在希望者に錦江町の雰囲気が伝えられるようにしています。
積極的に交流したい移住者と、町の人たちがうまくマッチしているように感じますね。
・居心地の良い場づくりにおいて意識していることはありますか?
よろっでのスタッフは、みんな熱量が高いので、それぞれのやりたいことをヒアリングしながら物事を進めるようにしています。
基本的にスタッフのみんなには、のびのびと過ごしてほしいと思っているので、困ったり目的がずれていると感じた時にはサポートに入ることもあります。
− 子どもと町をつなぐ。ツリーハウスプロジェクトについて
錦江町にある公園の活用について、実際に公園を使う機会の多い小学生と一緒に考えました。
背景には、
「公園に滑り台をつくったとしても、それが子どもたちにとって本当に必要なものなのかわからない。だから公園を利用する子どもたちから実際にアイデアを募集しよう」という思いがありました。
「どんな公園だったら良いか?」を子どもたちと一緒に考えながら、老若男女様々な世代が利用できる公園づくりをすることに。
その中で山中さんは、子どもたちが自発的に公園のあり方を考えられるようにワークショップから町長へのプレゼンをサポート。
そして子どもたちと一緒にクラウドファンディングにも挑戦しました。
小学校教諭の経験がある山中さんは、ツリーハウスプロジェクトを通して、学校以外での学びの場に手応えを感じているようです。
− ツリーハウスプロジェクトへの質問など
・プロジェクトのきっかけを教えてください。
空き地状態になった公園が目立ち、役場に公園をなんとかしてほしいとの意見が多く寄せられている状況がありました。
そこで実際に公園を利用する機会が多い小学生をはじめ、子育て世代の方、お年寄り、これから生まれてくる子どたちなど、色んな人に利用してもらえる場所になれば、と取り組みが始まりました。
・どのような人が関わっていますか?
小学3〜5年生がメインでプロジェクトに参加しています。
大人では海外の方も興味を持ってくださり、ワークショップの時には県外から足を運んでくれる方もいました。

・クラウドファンディング挑戦にあたって、気をつけていることはありますか?
目標達成のために、取り組みや資金額にあったリターンが大切だと考えています。
今回は教育の一環としての支援募集だったので、その旨を記載しました。リターンとしては、子どもたちからのお手紙やツリーハウス完成後の動画配信を考えています。
よろっでの改修の際に行ったクラウドファンディングのリターンは目標金額も高めに設定し、リターンも工夫しました。
宿泊券をはじめよろっでの「一日店長」券、地域企業と連携した内容も盛り込みました。
クラウドファンディングは、プロジェクトの目的をしっかり伝えることが重要です。
なぜ挑戦するのか、プロジェクトにかける思いなどはしっかり伝えた方が良いですね。
また会社の負債にならないよう金額調整も大切です。
・クラウドファンディングの支援者にはどのような人がいますか?
ツリーハウスは町内から100人、町外から66人。
基本的には町内向けに発信を行いましたが、町と関わりのない方も支援してくださっています。

− 2社の法人の立ち上げについて
・株式会社燈(あかり)について
「町のためにどう進んでいくかをみんなで考える町の会社が、燈」
株式会社燈は、2019年に設立。よろっでやシェアハウスの運営を行っています。
株主には役場職員から錦江町に来てからの友人など幅広く声をかけ、民間出資で立ち上げました。
町民の町に対する高いモチベーションを活かして「地元の人々みんなで主導権を持ち、一緒にやっていく」ビジネススタイルを実践しています。
・株式会社hinata
「あたたかい、居心地の良い場所をつくりたいという思い」
2021年6月に設立。協力隊や株式会社燈ではない立場で、「やりたいこと」を実現するために個人で立ち上げました。
現在は、テントサウナの事業化を目指して実験中です。
− ゲストにとっての半歩先とは?
ゲストや参加者にとっての”半歩先”について、主催者から問いかけがありました。
そもそも自分にとっての一歩とはなんだろう。
地域のために、だれかのために、自分のために、少しでも前に進もうと踏み出す半歩。
出演者それぞれが、これから挑戦したいことや今後の展望に思いを馳せながら語りました。
「地域の方とのコミュニケーションを大切にする」
「自分が一歩を踏み出すための方向やマインドを探る」
「自分を見つめなおす時間である」
といった”ちょっと踏み出す”ような意見が多い中、
山中さんは「半歩下がる」
「足を出しすぎない。ちょっとひっこめてみる」
「探りながら考えながらの半歩も良いかもしれないですね」と交流会を締めくくりました。
(ライター:友安麻里亜)
− 関連リンク
**
半歩先の歩き方MEET UPは、鹿児島県から「つなぐ・つながる連携の場づくり事業」を受託したNPO法人頴娃おこそ会が実施いたしました。